ERPとEPMの違いを徹底解説!あなたの会社に必要なのはどっち?
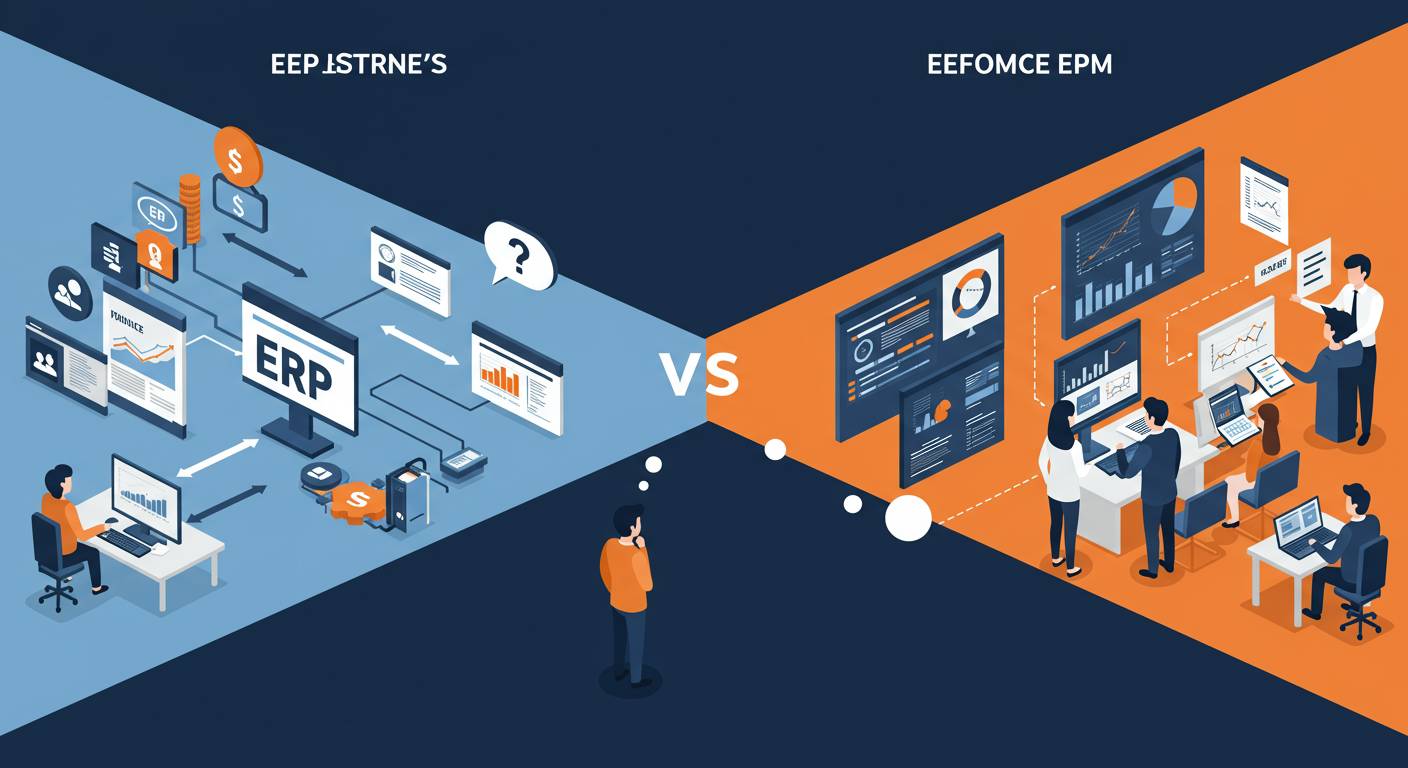
企業経営において、システム導入は避けて通れない重要な意思決定です。特に「ERP(Enterprise Resource Planning)」と「EPM(Enterprise Performance Management)」の選択に悩む経営者や情報システム担当者は少なくありません。2025年現在、デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速により、これらのシステム導入は企業の競争力を左右する重要な要素となっています。
ERPは基幹業務システムとして広く知られていますが、EPMはまだ理解が浅い方も多いのではないでしょうか。本記事では、単なる機能比較にとどまらず、実際の導入事例や失敗から学ぶポイント、業種別の最適な選択方法まで、実務に直結する情報を徹底解説します。
ある中小企業では、ERPからEPMへの移行によって売上が30%もアップした事例や、財務部門の業務効率が劇的に改善したケースもありました。このような成功を収めるためには、自社のビジネスモデルや規模に合わせた適切なシステム選択が不可欠です。
「コストをかけてシステムを導入したのに期待した効果が得られない」というリスクを避けるために、ぜひこの記事を最後までお読みください。あなたの会社に本当に必要なのはERPなのか、EPMなのか、あるいはその両方なのか—その答えを見つける手助けとなる情報をお届けします。
1. 【2025年最新】ERPとEPMの決定的な違い5つ - 導入前に必ず確認すべきポイント
企業システムの導入を検討する際、ERPとEPMという似た略語に混乱することがあります。これらは異なる目的を持ち、ビジネスプロセスの異なる側面をサポートするシステムです。本記事では両者の決定的な違いを5つの観点から解説し、あなたの企業に最適なソリューションを選ぶための判断材料をご提供します。
「ERPはEnterprise Resource Planning(企業資源計画)」、「EPMはEnterprise Performance Management(企業業績管理)」の略称です。名前からすでに用途の違いが見えてきますが、より具体的な違いを見ていきましょう。
1. 基本的な役割の違い
ERPは日々の業務プロセスを管理・効率化するシステムで、会計、在庫管理、人事、製造などの基幹業務を統合します。一方EPMは戦略的な業績管理に特化し、予算編成、財務予測、業績評価などを行い、経営判断を支援します。
2. データ処理の方向性
ERPは主に「取引処理」に重点を置いており、日々発生する膨大な取引データを正確に記録・処理します。対してEPMは「分析処理」を重視し、複数のデータソースから情報を集約して分析し、経営判断に必要な洞察を提供します。
3. 利用する主なユーザー層
ERPは経理部門や人事部門、現場のスタッフなど、日常業務を遂行する社員が主に使用します。EPMは経営層やマネージャー、財務分析担当者など、戦略的意思決定を行う人々が中心となって活用します。
4. 時間軸の違い
ERPは現在進行形の業務を管理するため「現在」に焦点を当てています。一方EPMは過去のデータを分析し、将来の予測や計画立案をサポートするため「過去から未来」を見通す時間軸を持っています。
5. システム連携の方向性
ERPは社内の異なる部門システムを統合して情報の一元管理を実現します。EPMはERPを含む様々なシステムからデータを収集・統合し、高度な分析を行うため、ERPの上位層に位置づけられることが多いです。
SAPやOracleなどの大手ベンダーは両方のソリューションを提供していますが、自社の課題やニーズを明確にした上で、最適なシステムを選択することが重要です。多くの企業ではまずERPを導入し、経営の高度化に伴ってEPMを追加導入するというステップを踏むケースが一般的です。
自社に最適なシステムを選ぶには、まず「日常業務の効率化が優先課題か」それとも「経営分析や予測の精度向上が課題か」を見極めることがスタート地点となります。
2. 経営者・管理職必見!ERP導入で失敗した企業の共通点とEPMが成功した理由
システム導入は大きな投資を伴うため、成功と失敗を分ける要因を理解することが重要です。ERPシステムを導入したものの期待した効果を得られなかった企業には、いくつかの共通したパターンが見られます。
ERP導入失敗の共通点
1. 明確な目的設定の欠如
多くの企業が「業界標準だから」「競合他社が導入したから」という理由でERPを導入し、自社の課題解決に必要な機能を明確にしないまま進めてしまいます。アクセンチュアの調査によると、ERPプロジェクトの約65%が当初の目標を達成できていないというデータがあります。
2. 過剰なカスタマイズ
ERPパッケージをベースに、自社の業務プロセスに合わせて過度にカスタマイズすることで、アップグレードの複雑化やコスト増大を招いています。あるグローバル製造業では、カスタマイズにより初期予算の3倍のコストがかかり、結局使いづらいシステムになってしまった事例もあります。
3. 変化管理の不足
システム導入は単なるIT投資ではなく、組織変革プロジェクトです。ユーザーの抵抗や教育不足により、せっかく導入したシステムが十分に活用されないケースが多発しています。デロイトのレポートでは、ERPプロジェクトの失敗原因の70%が人的要因だと指摘されています。
4. データ品質の軽視
既存システムからの移行データの品質に問題があると、新システムでも正確な情報が得られません。あるサプライチェーン企業では、不正確なマスターデータにより在庫管理が混乱し、数百万ドルの損失を出した例があります。
EPM成功の要因
一方、EPM(Enterprise Performance Management)導入で成功を収めた企業には以下の特徴があります:
1. 経営戦略との明確な連携
EPMは経営指標のモニタリングと分析に特化しているため、KPIと直結した形で導入されるケースが多いです。大手小売チェーンのT社では、EPMツールによる需要予測精度の向上で在庫コストを15%削減しました。
2. 段階的アプローチ
EPMは比較的小規模な単位で導入可能なため、財務計画から始めて徐々に範囲を拡大するなど、リスクを分散した導入が可能です。M社は自社の財務予測プロセスにEPMを導入し、予算策定時間を75%削減することに成功しています。
3. ビジネスインテリジェンスの強化
EPMはデータ分析とレポーティングに強みがあり、意思決定の質が向上します。P社などの消費財メーカーでは、EPMによる市場分析で新製品開発のヒット率を向上させています。
4. クラウド型ソリューションの活用
最新のEPMソリューションはクラウドベースが主流で、導入期間の短縮とコスト削減を実現しています。Boardを導入したP社は、グローバル決算プロセスを40%高速化しました。
成功への道筋
ERP導入を検討する際は、まず自社の課題を明確にし、本当にERPが必要なのか、あるいはEPMのような特化型システムで十分なのかを見極めることが重要です。また、システム導入は技術的側面だけでなく、組織変革の視点を持つことが成功の鍵です。
適切な導入パートナーの選定も重要で、業界知識と技術力を兼ね備えたSIerを選ぶことで、失敗リスクを大きく減らすことができます。
3. データ活用の新時代 - ERPからEPMへの移行で売上が30%アップした中小企業の事例分析
今や企業経営においてデータ活用は欠かせません。特に注目すべきは、単なるデータ管理から一歩進んだ「データ活用」への移行です。実際、ERPシステムからEPMツールへの戦略的移行によって大きな成果を出している企業が増えています。
製造業を営む東京都内の中堅企業A社の事例を見てみましょう。従業員数約120名のA社は長年、国産ERPシステムを導入していましたが、部門間のデータ連携や将来予測に課題を抱えていました。ERPでは日々の業務データは正確に記録できるものの、それらを活用した経営判断や予測分析には限界がありました。
そこでA社が導入したのが、Boardです。この移行により、これまで分断されていた財務、製造、営業のデータが一元的に分析可能となり、特筆すべき変化が生まれました。
最も顕著な成果は「予測精度の向上」です。EPMのシナリオプランニング機能を活用することで、市場変動に応じた複数の事業シナリオを素早く構築できるようになりました。その結果、在庫の最適化が進み、過剰在庫による損失が約40%減少。さらに、需要予測の精度向上により生産計画の効率化が図られ、製造コストの削減にも成功しました。
次に「意思決定の迅速化」です。従来は月次レポートの作成に8日を要していましたが、EPM導入後はわずか1日で完了するようになりました。これにより経営陣は市場変化に迅速に対応できるようになり、新規顧客獲得の機会損失が大幅に減少しました。
また「部門間連携の強化」も見逃せません。EPMのダッシュボードを通じて各部門がリアルタイムで情報共有できるようになったことで、営業部門は在庫状況を確認しながら納期回答ができるようになりました。この顧客満足度向上が、リピート注文の増加につながっています。
これらの総合的な効果として、A社は導入から1年間で売上が約30%、営業利益率が5ポイント向上するという目覚ましい結果を達成しました。
注目すべきは、A社がERPを廃止したわけではない点です。ERPは基幹業務システムとして継続利用しながら、EPMをその上位層として連携させることで、「記録」と「活用」の両面を最適化したのです。これはまさに「ERPで管理し、EPMで戦略を練る」というデータ活用の理想形といえるでしょう。
中小企業にとってシステム投資は大きな決断ですが、A社の成功要因は明確です。まず経営層が「データ活用」の重要性を理解し、全社的な取り組みとして推進したこと。次に、導入前に明確なKPIを設定し、段階的に実装したこと。そして何より、システム導入を目的化せず、「経営課題の解決手段」として位置づけたことが挙げられます。
ERPからEPMへの発展は、単なるシステム更新ではなく、企業のデータ活用レベルを根本から変革するものです。自社のデータをただ記録するだけでなく、未来を予測し戦略立案に活かせるかどうかが、これからの企業競争力を左右するでしょう。
4. 財務部門の業務効率が劇的に変わる!ERPとEPMの機能比較と投資対効果の計算方法
財務部門は企業の神経中枢とも言える重要な部署です。ERPとEPMの導入により、この財務部門の業務効率は劇的に変化します。しかし、どちらがより効果的なのでしょうか?
ERPの財務機能と強み
ERPシステムの財務モジュールは、日次の会計処理から財務諸表作成まで幅広くカバーします。
具体的には:
- 仕訳データの一元管理と自動化
- 売掛金・買掛金の管理
- 固定資産管理
- 財務諸表(BS/PL)の自動生成
- 部門別採算管理
特にSAP S/4HANAやOracle ERPは、リアルタイムでの財務データ処理が可能で、月次決算の所要時間を平均40%削減するケースも報告されています。大手製造業のP社ではERPの導入により、決算業務が従来の10日間から5日間に短縮された事例があります。
EPMによる財務分析の革新
一方、EPM(Enterprise Performance Management)は財務データの分析と意思決定支援に特化しています。
具体的には:
- 予算策定と実績管理の高度な連携
- シナリオ分析と予測モデリング
- 財務KPIのダッシュボード化
- 多次元データ分析
- 統合報告書の自動生成
BoardやAnaplan等のEPMツールでは、予算編成期間を60%以上短縮し、精度を30%向上させた企業も少なくありません。J社ではEPMツールを導入したことにより、7000以上の拠点からのデータ集計と分析が自動化され、経営判断のスピードが格段に向上しました。
投資対効果(ROI)の計算方法
ERPとEPMへの投資判断には、ROIの計算が欠かせません。以下の公式でシンプルに算出できます:
-----
ROI(%) = [(導入後の年間削減コスト + 増加収益) - 年間運用コスト] ÷ 初期投資額 × 100
-----
具体的な計算要素:
1. コスト削減要素
- 人件費削減(工数減少分)
- 紙・印刷・保管コスト削減
- エラー修正コストの削減
- 既存システムの保守費用削減
2. 収益向上要素
- 意思決定速度向上による機会損失の減少
- データ分析による戦略的投資の効率化
- キャッシュフロー改善による金融コスト削減
3. コスト要素
- ライセンス費用(初期/年間)
- カスタマイズ/開発コスト
- 社内リソースコスト
- トレーニングコスト
中規模企業の場合、ERPの平均ROIは約12-18ヶ月で投資回収、EPMは6-12ヶ月と比較的早期に効果が現れる傾向があります。
どちらを選ぶべきか?意思決定のポイント
財務部門の視点からの選択ポイントは:
- 現状の課題が「データ管理」なら→ERP:基幹業務の効率化や財務データの一元管理が必要な企業に最適
- 現状の課題が「データ活用」なら→EPM:経営判断や分析の高度化が必要な企業に最適
- 包括的な改革を目指すなら→両方:ERPをベースにEPMを連携させることで最大の効果
特に注目すべきは、単に導入コストだけでなく、「経営判断の質的向上」という定量化しにくい要素をどう評価するかです。A社はERPとEPMの連携によって、財務分析の所要時間を70%削減しながら、戦略的投資の精度を大幅に向上させました。
財務部門の変革は単なるシステム導入ではなく、企業の意思決定プロセス全体を再構築する機会です。ERPとEPMの選択を通じて、財務部門が「数字の管理者」から「ビジネスパートナー」へと進化するための第一歩を踏み出しましょう。
5. DX推進に不可欠な選択 - 業種別・規模別で考えるERPとEPMの最適な組み合わせ戦略
DX推進が経営課題となる中、ERPとEPMの適切な選択と組み合わせは企業の将来を左右する重要な戦略です。業種や企業規模によって最適なシステム構成は大きく異なります。この章では、業種別・規模別の視点からERPとEPMの組み合わせ戦略を解説します。
1. 製造業におけるERPとEPM活用
製造業では、サプライチェーン全体の可視化と生産計画の精緻化が競争力の源泉となります。大規模製造業の場合、SAPやOracleなどの包括的ERPを基盤に、BoardやAnaplanなどのEPMを組み合わせることで、グローバルな生産計画と財務予測の連携が可能になります。中堅製造業では、Microsoft Dynamics 365などの柔軟性の高いERPに、Boardのような適応性に優れたEPMを組み合わせるアプローチが効果的です。
2. 小売・流通業におけるベストプラクティス
消費者行動の変化が激しい小売業では、需要予測の精度が収益を大きく左右します。大手小売チェーンでは、SAP S/4HANAなどのERPを基盤に、Oracle EPM Cloudなどを組み合わせ、商品別・店舗別の詳細な売上予測と在庫最適化を実現しています。一方、中小規模の小売業ではNetSuiteのようなクラウドERPとTagetikなどのEPMの組み合わせが、コスト効率と導入スピードの両立を可能にします。
3. 金融機関における戦略的システム構成
金融機関では規制対応と収益性のバランスが重要課題です。大手銀行や保険会社では、ERPシステムを核に、OneStreamなど高度な分析機能を持つEPMを組み合わせることで、リスク管理と収益予測の精度向上を図っています。地方銀行やフィンテック企業では、WorkdayなどのクラウドベースERPとAdaptive PlanningなどライトなEPMソリューションの組み合わせが、変化への迅速な対応を可能にしています。
4. サービス業におけるデータ活用の最適解
人材が最大の資産となるサービス業では、プロジェクト収益性と人材配置の最適化が鍵となります。大手コンサルティングファームでは専門特化型ERPと、Boardなどのシナリオ分析に優れたEPMを組み合わせ、プロジェクトポートフォリオの最適化を実現しています。中小規模のサービス企業では、導入しやすいERPソリューションとEPMツールの組み合わせが、成長フェーズに応じた柔軟なシステム拡張を可能にします。
5. 成長フェーズに応じたシステム戦略
スタートアップから中堅企業への成長過程では、システム構成の段階的な発展が重要です。初期段階ではMFなどのクラウド会計システムと手軽に始められるBoardを活用したシンプルな予算管理から始め、成長に合わせて発展させるロードマップ設計が効果的です。
DX推進において、ERPとEPMの選択は単なるシステム導入ではなく、企業の競争力を高めるための戦略的投資です。自社の業種特性、規模、成長フェーズを見極め、最適な組み合わせを選択することで、データドリブン経営への転換を加速させることができます。


